1-2 商業簿記との違い(原価と仕訳)
商業簿記との違いを解説します。特に、商業簿記では登場しない「原価」という用語と、工業簿記の仕訳の考え方を解説します。
※日商簿記3級で学習する「仕訳の基本」が理解できていることを前提とした解説
工業簿記と商業簿記との違い
商業簿記では、例えば「商品」「仕入」といった勘定科目を使用して、「モノを仕入れて取引先に販売する」という取引の仕訳を学習します。会社の業界でいえば、「商社」「コンビニエンスストア」「スーパー」「百貨店」「本屋さん」「八百屋さん」などが該当します。
これに対して、工業簿記を使用するのは、自動車、家電、食品、衣服、建物、ゲームなど、モノ(製品)を製造して販売する会社です。
いわゆる「メーカー」と呼ばれる会社が工業簿記を使用します。
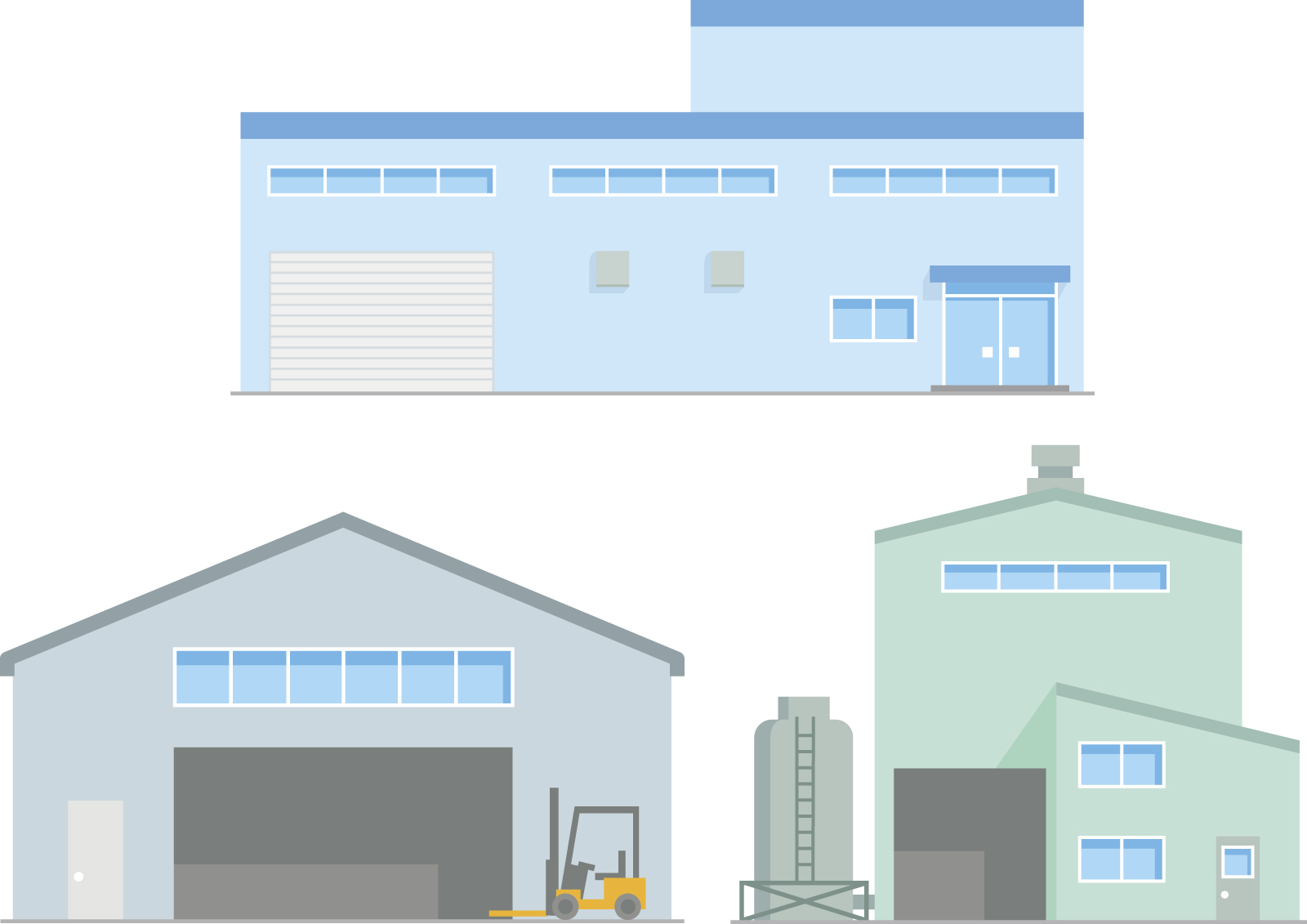
以上から、商業簿記だけでなく工業簿記が分かれば、メーカーの活動が簿記を通して理解できるようになります。
<Check>商業簿記と工業簿記の違い
- ・商業簿記 = モノを仕入れて、取引先に販売する取引を記帳
- ・工業簿記 = モノの製造と販売に関する取引を記帳
原価とは
改めて、「原価(げんか)」とは、モノ(製品)を作るのに要した支出額(コスト)をいいます。
「費用」と似ていますが異なる用語です。
商業簿記で学習する費用の勘定科目(仕入・減価償却費・給料・水道光熱費・支払家賃等の沢山の勘定科目)は、
「商品を仕入れて販売するための活動」
として発生しました。
これに対して、「原価」とは、
「製品を製造するための活動」
として発生します。
<補足>製造原価
- ・「モノ(製品)を作るのに要した支出額(コスト)」は、厳密には「製造原価」といいます(原価は製造原価より広い活動を含む)。
- ・しかし、一般的に「原価」と言った場合には「製造原価」のことを示すことから、本書でも「原価=製造原価」として解説しています。
費用と原価で同じ勘定科目を使用する
例えば、「建物の減価償却費」を考えると、
「本社ビル」の場合は「費用」
「工場」の場合は「原価」
になります。なぜならば、工場は製品を製造するために使用しているからです。
建物だけでなく、備品や自動車も同じです。「工場で使用する備品」や「材料を運搬するためのトラック」などの減価償却費は、費用ではなく「原価」です。
工場を所有ではなく賃借している場合の「支払家賃」も「原価」であれば、工場で働く人達の「給料」も「原価」です。
このように、同じ勘定科目であっても、「費用」になる場合もあれば、「原価」になる場合もあります。
原価を簿記の視点で説明した場合
原価を簿記(工業簿記)の視点で説明すると、次の通り。
「原価」とは、製品の製造に関する会社の活動・取引のうち、
製造している間は「仕掛品(資産)」
完成した時に「製品(資産)」
販売した時に「売上原価(費用)」
になるもの。
※仕掛品になる前は「材料」「賃金・給料」などの勘定科目に集計。
※仕掛品などの用語は、後の章で解説します。
特に、製造中、つまり、「仕掛品」の状態が「原価」の範囲といえます。
製品になった後は「商品」と同じく、販売されれば損益計算書上の「売上原価(費用)」になります。
原価は製造原価報告書に記載される
商業簿記で学習する財務諸表(貸借対照表・損益計算書)には、「資産・負債・純資産・収益・費用(いわゆる簿記の5要素)」に属する科目とその金額を表示しますが、原価は表示しません。
原価に関する活動は、「製造原価報告書(C/R)」という表に掲載します(詳細は「第12章 損益計算書と製造原価報告書」を参照)。
原価と仕訳
上記「原価を簿記の視点で説明した場合」で説明した通り、原価は段階的に「仕掛品(資産に属する勘定科目)」「製品(資産に属する勘定科目)」「売上原価(費用に属する勘定科目)」に集計されることから、「原価」は「資産」や「費用」と同じく
「原価の発生(増加)は借方」
「原価の減少は貸方」
に記入します。
(補足)原価と勘定科目
一般的には、原価については「資産・負債・純資産・収益・費用」とは同じ位置付けで勘定科目や仕訳を解説しません。
しかし、分かりやすさと解説のしやすさから、本書では、「仕掛品(資産に属する勘定科目)」「製品(資産に属する勘定科目)」「売上原価(費用に属する勘定科目)」のように、
「原価に属する勘定科目」
として解説します。
※このような説明をもって学習した方が、後々、経理実務で原価を担当することになった場合にも役立つはずです。
<Check>原価とは(簿記の視点)
- ・製造に関連する活動・取引
- ・製造前:「材料(資産に属する勘定科目)」「賃金・給料(原価に属する勘定科目)」などに集計
- ・製造中:「仕掛品(資産に属する勘定科目)」に集計
- ・完成後:「製品(資産に属する勘定科目)」に集計
- ・販売後:「売上原価(費用に属する勘定科目)」に集計
- ・原価の活動は「製造原価報告書(C/R)」に表示
<Check>原価と仕訳
- ・資産や費用と同様に記帳
- ・原価の発生(増加)→「借方」に記入
- ・原価の減少→「貸方」に記入
