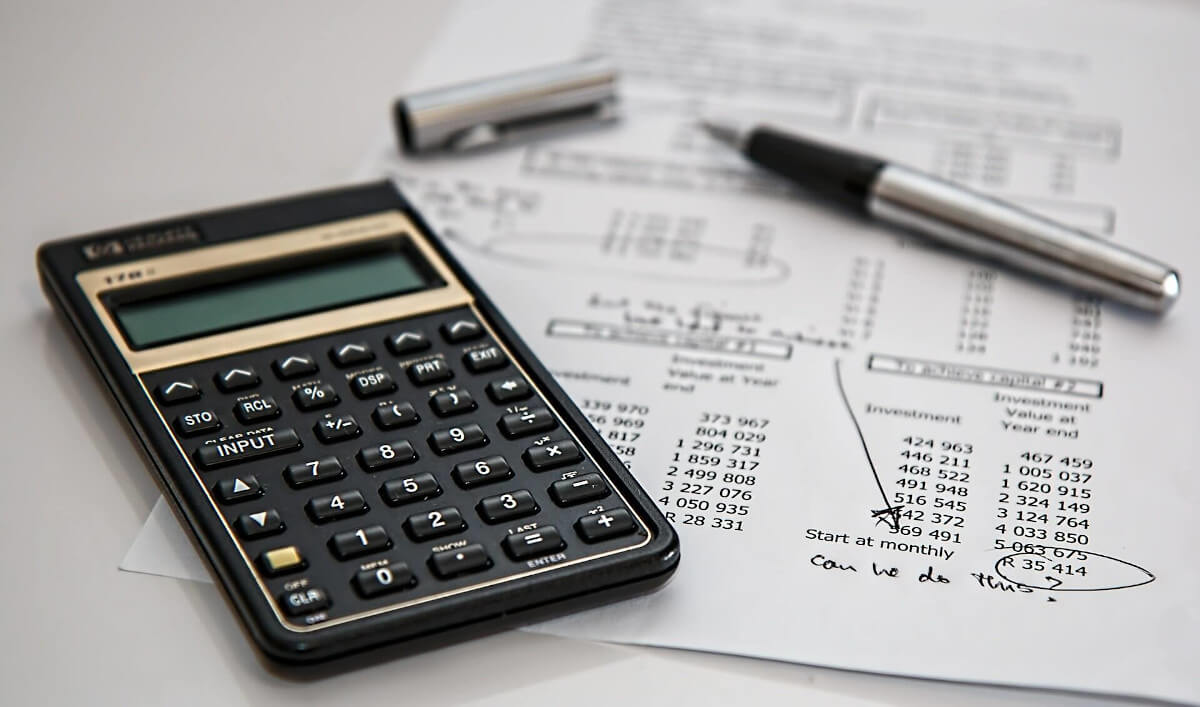15-1 連結会計
連結会計とは
連結会計とは、親会社と子会社などからなる企業グループを1つの会社とみなして、連結財務諸表(連結決算書)を作成するための会計をいいます。
親会社と子会社とは
ある会社が、他の会社を実質的に支配している場合に、支配する側の会社を「親会社」、支配される側の会社を「子会社」といいます。
支配力基準
ここで、「実質的に支配している」とは、様々なケースが考えられますが、最も一般的なケースは、「子会社が発行している株式総数の過半数を親会社が保有している状態」をいいます。
「過半数」とは、半分を超えた状態です。例えば1,000株を発行している場合の500株を保有している状態、すなわち50%は過半数とはいえません。51%は過半数に該当します。
このように、子会社かどうかの判定を「実質的な支配」に基づき判定するルールを、支配力基準といいます。
子会社化の目的
株式の過半数の保有は、子会社の株主総会のほとんどの決議を、親会社の一存で決めることができる、ということを意味します。
株主総会のほとんどの決議は、普通決議といい、株主総会に参加した株主の議決権数(ここでは、イコール株式数と考えて差し支えありません)のうち、過半数をもって決議します。従って、過半数を保有しているということは、普通決議は全て親会社が決めることができる、ということを意味します。
株式数の過半数の保有が、その会社を実質的に支配している、といえるのは、以上の効果があるからです。
<補足>支配力基準
- 支配力基準には、他にも様々なケースに応じた、詳細なルールが存在します。
- ※簿記2級の範囲外
企業集団(企業グループ)
親会社を頂点とする、全ての子会社と関連会社を含めた集団を、「企業集団(企業グループ)」といいます。
<補足>関連会社
- ・ある会社が、株式取得などを通じて、子会社のように支配とまではいかないが、他の会社に重要な影響を与えることができる場合、この「他の会社」のことを「関連会社」といいます。
- ・子会社の支配力基準に対して、関連会社かどうかは「影響力基準」で判定します。簿記2級では「20%以上50%以下の株式を取得した場合」が該当します。
連結財務諸表(連結F/S)とは
連結財務諸表とは、親会社が株主など外部の関係者に提出・報告することを目的として作成される、企業グループの財政状態や経営成績を表すための書類をいいます。
財務諸表は、英語で「F/S(Financial Statement)」です。従って、「連結F/S」ということがあります。
連結財務諸表には、「連結貸借対照表」「連結損益計算書」などがあり、それぞれ「連結B/S」「連結P/L」ともいいます。
連結会計の特徴
連結会計は、親会社や子会社を同一の企業グループとして、1つの会社とみなします。
「1つの会社とみなす」ということは、「親会社や子会社といった、企業グループ内の取引は、企業グループ内部の取引とみなす」ということです。
内部取引
例えば、親会社が子会社に商品を販売した場合、個別の決算書では、会社外部の取引として記帳します。
従って、この取引は、親会社の損益計算書では売上高と売上原価として表示し、子会社の貸借対照表に商品などの資産として、表示します。
しかし、同一の企業グループとして捉える連結決算書では、単に企業グループ間の内部取引とみなします。
従って、連結決算書には、親会社の損益計算書に表示した売上高や売上原価、および子会社の貸借対照表に表示した商品などの資産からは、この内部取引を消去するように、連結上の修正仕訳を行います。
連結修正仕訳
このような修正仕訳を、「連結修正仕訳」といいます。
上の例では、売上高や仕入(売上原価)、商品以外にも、掛け販売であれば、親会社で売掛金、子会社で買掛金が発生します。従って、これらの債権債務も含めて相殺消去する(計上をゼロにする)ように、連結修正仕訳を作ります。
親会社で、この売掛金に対して貸倒引当金を設定していた場合には、その貸倒引当金も計上しないように修正しなければなりません。
親子会社間の内部取引には、商品販売と仕入の他にも、土地の売買取引が代表的な例です。
資本連結
連結修正仕訳には、企業グループ内部の取引に関するものの他に「資本連結」というものがあります。
親会社が子会社の株式を取得して実質的な支配を形成した時に、親会社が保有する子会社株式と子会社の株主資本等(純資産)を相殺消去するとともに、のれんを識別する会計処理をいいます。
連結決算手続き
親会社と子会社それぞれの決算手続きとは、別の手続きとして、連結決算手続きを行います。
手続きの流れは次の通り。
(手順0)全ての会社の個別財務諸表を完成させる
連結決算手続きは、親会社と各子会社の決算手続きが完了し、各社の財務諸表を事前に用意しておいてから、開始します。
<補足>個別財務諸表
- 企業グループに属する各社の財務諸表を、個別財務諸表といいます。
(手順1)個別財務諸表の合算
親会社と子会社の全ての個別財務諸表を合算します。
合算とは、各社の個別B/S、個別P/Lの各表示科目の残高を、科目毎に合計することをいいます。
(手順2)連結修正仕訳
(手順1)の単純合算のままでは、内部取引が残高に含まれたままです。
そこで、上述で説明した資本連結や内部取引を調べて、連結修正仕訳を行います。
単純合算の各科目残高に、連結修正仕訳を反映させることで、内部取引を消去できます。
(手順3)連結精算表の作成
単純合算と連結修正仕訳の各科目残高を、全て反映させた精算表を、作成します。
これを、「連結精算表」といいます。
(手順4)連結財務諸表の作成
連結精算表をもとに、連結財務諸表を作成します。
簿記2級では、連結貸借対照表(連結B/S)と連結損益計算書(連結P/L)を学習します。
連結決算の特徴
親会社と子会社それぞれの決算手続き(個別の決算)とは、別の手続きとして、連結決算手続きを行います。
上に述べた資本連結や内部取引といった連結修正仕訳は、個別の決算の仕訳に含めてはいけません。必ず、連結決算用の仕訳として、個別の決算とは別に記録します。
連結決算の仕訳の特徴
連結決算は、親会社と子会社の決算書(B/SとP/L)からスタートします。
従って、連結決算の仕訳は、決算書上の表示科目を使って仕訳します。
例えば、商品の仕入は、普通は仕入勘定を使いますが、連結決算では「売上原価」や「当期商品仕入高」といった科目で仕訳します。