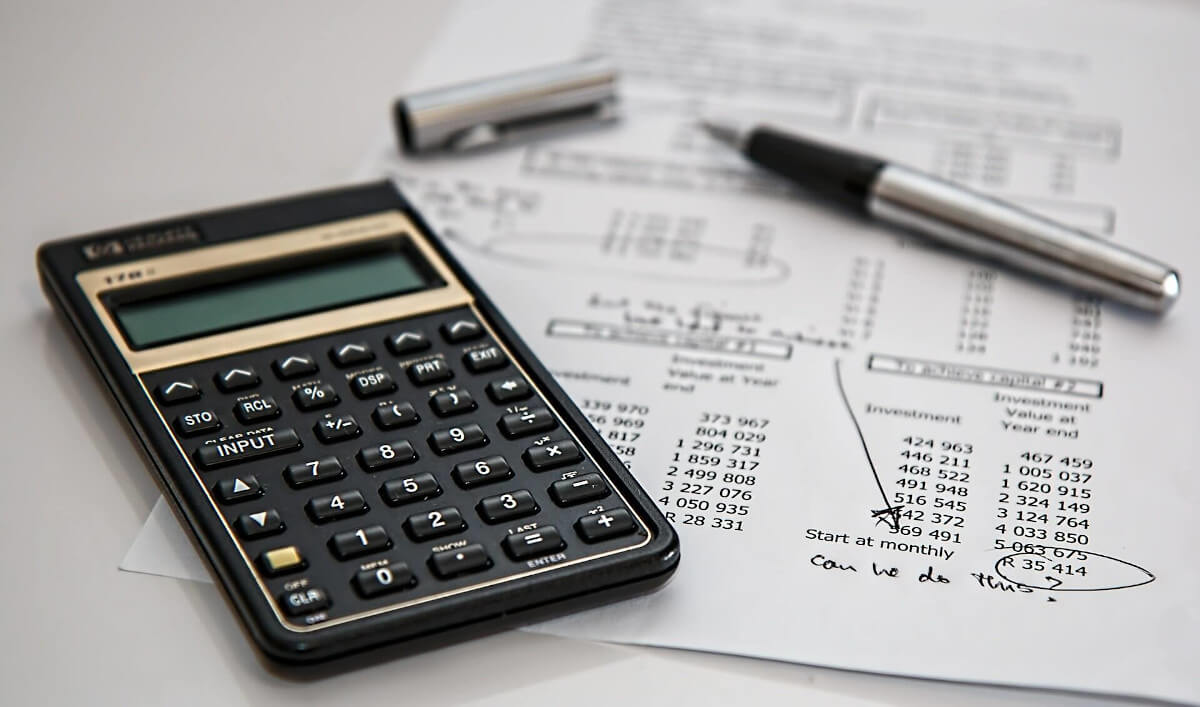15-3 開始仕訳
開始仕訳とは
「開始仕訳」とは、過去度の連結決算に行った連結修正仕訳のことをいいます。
例-資本連結
支配獲得時の資本連結を例として、開始仕訳を説明します。
例えば、×1年3月31日にA社はB社の株式80%を取得しました。この時点で、50%を超える株式を取得し支配獲得に該当するため、B社はA社の子会社になりました。
この時には、前回解説した通り、支配獲得時の連結修正仕訳(資本連結の仕訳)を記帳します。仮に、正ののれんが発生した場合には次の通り。
<×1年3月31日>
| 取引 | のれん | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支配獲得 | 正 | 資本金 | ××× | 子会社株式 | ××× |
| 資本剰余金 | ××× | 非支配株主持分 | ××× | ||
| 利益剰余金 | ××× | ||||
| のれん | ××× |
次年度の仕訳
それでは、次年度の×2年3月31日には、どのような仕訳を行うでしょうか?
この点が、個別(通常)の財務諸表の決算仕訳(決算整理仕訳)とは、異なる点です。
結論を書くと、×1年3月31日の連結修正仕訳を×2年3月31日でも、同じく仕訳しなければなりません。
開始仕訳の目的
なぜならば、連結修正仕訳は、親会社や子会社の個別決算の仕訳の外で行われるため、×1年3月31日に連結修正仕訳を記帳したとしても、×2年3月31日の個別の親会社や子会社の財務諸表(決算書)には、×1年3月31日に記帳した連結修正仕訳は反映されていないからです。
従って、支配獲得した年度以降の連結修正仕訳には、過去の年度で記帳した連結修正仕訳を含めて、仕訳しなければならない、ということになります。
これが、「開始仕訳」です。
開始仕訳の形式
次の点を除き、取引が発生した年度の連結修正仕訳と、同じ仕訳です。
<開始仕訳のポイント>
- ・損益の勘定科目は利益剰余金勘定に修正する
- ・その他の点は連結修正仕訳と同じ
利益剰余金に修正する理由
損益の勘定科目を利益剰余金に修正するのは、損益の勘定科目を開始仕訳で、そのまま仕訳してしまうと、開始仕訳を行なった年度の損益になってしまうからです。
この損益は、取引が発生した年度に属する損益であるはずです。
P/L上の損益は、B/Sの繰越利益剰余金として、次期に繰り越します。つまり、開始仕訳を行なった年度では、繰越利益剰余金になっているはずです(損失の場合は、繰越利益剰余金からマイナス)。
そして、連結決算では、繰越利益剰余金や利益準備金といった利益の剰余金科目は、全て「利益剰余金」で仕訳します。
従って、取引が発生した年度の次の年度以降では、損益ではなく、「利益剰余金」として会計処理する必要があるのです。
以上の理由から、損益の勘定科目は開始仕訳では、「利益剰余金」に修正して仕訳します。
今回の例の開始仕訳
×2年3月31日の開始仕訳は、次の通り(×1年3月31日の連結修正仕訳と同じ)。
<×2年3月31日>
| 取引 | のれん | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始仕訳 | 正 | 資本金 | ××× | 子会社株式 | ××× |
| 資本剰余金 | ××× | 非支配株主持分 | ××× | ||
| 利益剰余金 | ××× | ||||
| のれん | ××× |
今回の資本連結では、損益の勘定科目がありませんので、結果的に、最初の年度の連結修正仕訳と同じになります。
まとめ
今後の例でも、開始仕訳が登場します。その際にも、開始仕訳については具体例に解説します。