工程別総合原価計算の解き方と累加法、前工程費
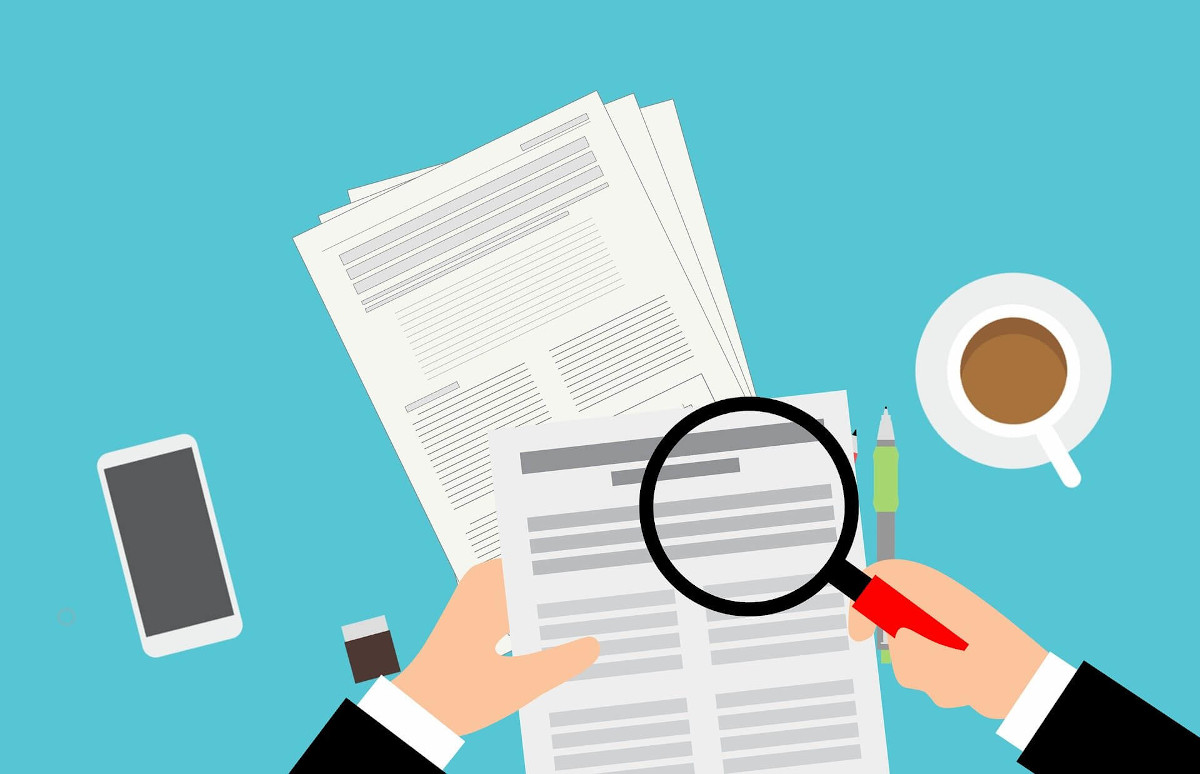
記事最終更新日:2021年12月20日
記事公開日:2016年11月26日
組別総合原価計算の解き方と累加法、前工程費について問題例を使って解説します。
工程別総合原価計算とは
工程別総合原価計算とは、1つの工程ではなく、複数の工程に分けて連続生産(大量生産)する場合で、工程毎に工程製品の総合原価を計算する場合に適用する製品別計算をいいます。
引用元:原価計算基準
「総合原価計算において、製造工程が二以上の連続する工程に分けられ、工程ごとにその工程製品の総合原価を計算する場合(この 方法を「工程別総合原価計算」という。)には、一工程から次工程へ振り替えられた工程製品の総合原価を、前工程費又は原料費として次工程の製造費用に加算する。」
工程毎に総合原価を計算したい場合に適用するのが工程別総合原価計算です。工程毎にボックス図を用いて単純総合原価計算を行うイメージです。
例えば、2つの工程に分けて原価計算を行う場合には2つのボックス図を描いて計算します。
問題例(工程別総合原価計算と累加法、前工程費)
今回は設例を用いて解説します(簿記2級のレベルでは「易」レベル)。
<問題例-工程別総合原価計算>
- 当社は切抜工程と裁縫工程という2つの製造工程で1種類のズボンを生産しており、原価計算方法は工程別総合原価計算を採用している。
- 今月の原価活動の状況と必要なデータは次の通り。
- ・原料費と前工程費は製造工程の始点に投入し、加工費は平均的に投入する。
- ・原価を完成品と月末仕掛品に配分する方法として、先入先出法を用いる。
- ・当月の切抜工程の完成品は全て裁縫工程へ投入した。
- (問1)切抜工程の完成品原価(前工程費)と月末仕掛品原価を求め、裁縫部門への振替仕訳をきりましょう(「仕掛品-切抜工程」「仕掛品-裁縫工程」の各勘定科目を用いること)。
- (問2)裁縫工程の完成品原価と月末仕掛品原価を求め、完成品原価計上の仕訳をきりましょう(「仕掛品-裁縫工程」の勘定科目を用いること)。
1.生産データ
| 項目 | 切抜工程 | 裁縫工程 |
|---|---|---|
| 月初仕掛品 | 500本(20%) | 400本(40%) |
| 当月投入 | ○○本 | ○○本 |
| 合計 | ○○本 | ○○本 |
| 月末仕掛品 | 300本(50%) | 700本(60%) |
| 完成品 | 2,000本 | 1,700本 |
2.原価データ
| 項目 | 切抜工程 | 裁縫工程 | |
|---|---|---|---|
| 月初仕掛品 | 原料費 | 59,000円 | -円 |
| 前工程費 | -円 | 226,400円 | |
| 加工費 | 44,300円 | 172,350円 | |
| 当月製造費用 | 原料費 | 223,200円 | -円 |
| 前工程費 | -円 | ○○円 | |
| 加工費 | 928,650円 | 1,395,520円 | |
解答
<解答(問1)-切抜工程の完成品総合原価(前工程費)と月末仕掛品原価>
- 完成品総合原価 1,150,000円
- 月末仕掛品原価 105,150円
<解答(問1)-前工程費の振替仕訳)>
- (借方)仕掛品-裁縫工程 1,150,000 (貸方)仕掛品-切抜工程 1,150,000
<解答(問2)-裁縫工程の完成品総合原価と月末仕掛品原価>
- 完成品総合原価 2,242,730円
- 月末仕掛品原価 701,540円
<解答(問2)-完成品原価計上の仕訳)>
- (借方)製品 2,242,730 (貸方)仕掛品-裁縫工程 2,242,730
(1)ボックス図と生産・原価データの記入
「切抜工程(布の切抜)→裁縫工程(布の縫い合わせ)」という工程の順番でズボンを製造します。工程別原価計算ですので切抜工程と裁縫工程とに分けて、それぞれのボックス図を描いて原価計算を行っていきます。
勘定連絡図では、「仕掛品-〇〇工程」といったように工程の数だけ工程別の仕掛品勘定があって順番に繋がっていき、最後の工程が製品勘定につながるように解説されることが一般的です。
ボックス図は次の通り。
| 仕掛品-切抜工程 | |
|---|---|
| 月初仕掛品 500本(100本) | 完成品 2,000本(2,000本) |
| 59,000円(44,300円) | |
| 当月投入 1,800本(2,050本) | |
| 223,200円(928,650円) | 月末仕掛品 300本(150本) |
| 仕掛品-裁縫工程 | |
|---|---|
| 月初仕掛品 400本(160本) | 完成品 1,700本(1,700本) |
| 226,400円(172,350円) | |
| 当月投入 2,000本(1,960本) | |
| ?円(1,395,520円) | 月末仕掛品 700本(420本) |
ボックス図の書き方や加工費の数量計算(進捗度と換算量)、度外視法は下記の記事を参照。
(2)累加法と前工程費
累加法とは、工程別原価計算で採用される計算方法の一つであり、最初の工程の直接材料費と加工費を前工程費(まえこうていひ)として扱い、そのまま次の工程に引き継ぐ方法のことをいいます。
※他の計算方法として非累加法がありますが、簿記2級(工業簿記)では累加法のみが出題されます。
本問では、切抜工程で完成した原価(直接材料費+加工費)が前工程費として、次の裁縫工程に引き継がれます。
裁縫工程では原料費は発生せず、工程の開始段階で前工程費が投入され、進捗段階に応じて加工費が投入されます。
つまり、「次工程の原料費=前工程費」という考えで差し支えありません。
工程別総合原価計算のポイントはこの点のみであり、その他は単純総合原価計算と同じ要領で計算すれば解けます。
(3)完成品原価と月末仕掛品の計算
次にボックス図の数字に従って、原料費と加工費それぞれの完成品原価と月末仕掛品原価を求めます。
問題文より計算には先入先出法を使います。
どちらの工程も「先入先出法 → 当月投入数量 > 月末仕掛品数量 → 月末仕掛品原価は当月投入原価のみ。月初仕掛品は含まれない」となるので、先に月末仕掛品原価を求めて、その後に差額計算によって完成品原価を求めます。
<ポイント-切抜工程の完成品原価と月末仕掛品原価の計算(先入先出法)>
- ・月末仕掛品(原料費) =(223,200円 ÷ 1,800本)× 300本 = 37,200円
- ・月末仕掛品(加工費) =(928,650円 ÷ 2,050本)× 150本 = 67,950円
- ・月末仕掛品原価 = 37,200円 + 67,950円 = 105,150円 ←(問1)の解答
- 完成品原価(前工程費)=(59,000+44,300)+(223,200円+928,650円)-(37,200円+67,950円)=1,150,000円 ←(問1)の解答
| 仕掛品-切抜工程 | |
|---|---|
| 月初仕掛品 500本(100本) | 完成品 2,000本(2,000本) |
| 59,000円(44,300円) | 1,150,000円←前工程費 |
| 当月投入 1,800本(2,050本) | |
| 223,200円(928,650円) | 月末仕掛品 300本(150本) |
| 37,200円(67,950円) | |
<ポイント-裁縫工程の完成品原価と月末仕掛品原価の計算(先入先出法)>
- ・月末仕掛品(前工程費)=(1,150,000円 ÷ 2,000本)× 700本 = 402,500円
- ・月末仕掛品(加工費) =(1,395,520円 ÷ 1,960本)× 420本 = 299,040円
- ・月末仕掛品原価 = 402,500円 + 299,040円 = 701,540円 ←(問2)の解答
- 完成品原価 =(226,400円 + 172,350円)+(1,150,000円 + 1,395,520円)-(402,500円 + 299,040円)= 2,242,730円 ←(問2)の解答
| 仕掛品-裁縫工程 | |
|---|---|
| 月初仕掛品 400本(160本) | 完成品 1,700本(1,700本) |
| 226,400円(172,350円) | 2,242,730円 |
| 当月投入 2,000本(1,960本) | |
| 1,150,000円(1,395,520円) | 月末仕掛品 700本(420本) |
| 402,500円(299,040円) | |
(4)仕訳(前工程費の振替と完成品原価の計上)
切抜工程の完成品(前工程費)は裁縫工程へ振り替え、完成品は裁縫工程から製品に振り替える仕訳をきります。
本問では、「仕掛品-切抜工程」「仕掛品-裁縫工程」の各勘定科目を使用するように指示があるので、左記の勘定科目を記入して仕訳します。
<解答(問1の再掲)-前工程費の振替仕訳)>
- (借方)仕掛品-裁縫工程 1,150,000 (貸方)仕掛品-切抜工程 1,150,000
<解答(問2の再掲)-完成品原価計上の仕訳)>
- (借方)製品 2,242,730 (貸方)仕掛品-裁縫工程 2,242,730
解答のポイント
最後に本問の解答のポイントを掲載します(総合原価計算共通の解き方の部分を含む)。
<解答のポイント-工程別総合原価計算と累加法、前工程費>
- ・問題の生産・原価データや仕損・減損の設定を読み取り、ボックス図を正確に描く
- ・先入先出法なのか平均法なのかを読み取り、仕損・減損の発生時点の情報と併せて完成品原価と月末仕掛品原価を計算
- ・仕損・減損の処理は度外視法(発生時点により2通りの方法)
- ・前工程の完成品原価を前工程費として次工程の始点に投入(原料費と同じ計算)
- ・仕訳:「仕掛-〇〇工程」といった勘定科目が出題される場合あり(問題の指示に従う)
関連記事(個別・実際原価計算)
※電子書籍WEB版(フリー)の一覧は「PDCA会計 日商簿記2級 工業簿記詳解-傾向と対策(電子書籍WEB阪)」内の「第5章 個別原価計算」及び「第6章 総合原価計算」に掲載
- ・製品別計算とは|概要、種類と手続き
- ・個別原価計算とは|概要と手続きの流れを解説
- ・製造指図書と原価計算表、補修指図書とは|集計の仕方と仕訳
- ・総合原価計算とは|種類と手続き
- ・加工費、進捗度と計算方法|換算量
- ・ボックス図と書き方|計算方法も解説
- ・度外視法とは|仕訳と計算方法の解き方
- ・等級別総合原価計算の解き方|等価係数の計算方法と仕訳
- ・組別総合原価計算の解き方|組間接費の計算方法と仕訳
- ・工程別総合原価計算の解き方と累加法、前工程費
日商簿記ネット試験の模擬問題
ネット試験の操作に慣れることで合格率アップにつながります。
電子書籍WEB版
日商簿記3級・2級(商業簿記・工業簿記)テキストをフリーで閲覧できます。
仕訳問題
PDCA会計が発売・公開中の電子書籍とアプリに掲載の仕訳問題を当サイト上で全問解けます。
仕訳問題アプリ
・日商簿記3級の最新試験範囲に対応
・基本の仕訳問題150問を掲載(全問無料)
・シンプル画面&分かりやすい操作
・アプリ初心者も安心。プライバシーに配慮。課金なし。アカウント登録なし。
・Google Playの厳しい審査を通過
