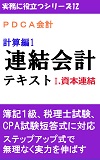取引高(連結会社間取引)の相殺消去と仕訳を解説

記事最終更新日:2022年10月5日
記事公開日:2022年6月18日
取引高は、債権債務と並び内部取引(連結会社間取引)の最も代表的な科目です。
本記事では、連結財務諸表上の取引高の仕訳、会計処理・基準について基本事項を解説します。
連結会社間取引とは
連結会社間取引とは、親会社と子会社、又は子会社間の取引をいいます。「内部取引」ということもあります。
取引高
売上高や売上原価などをいい、商品売買の内部取引(ダウンストリーム、アップストリーム)で発生します。
未実現損益
取引高の内部取引で発生した損益のうち、外部に販売していない部分を「未実現利益」といいます。
連結会社相互間の取引によって取得した棚卸資産、固定資産その他の資産に含まれる未実現損益は、全額を消去します。
会計処理・基準
連結会社相互間における商品の売買その他の取引における項目は相殺消去します(企業会計基準第22号 連結財務諸表上に関する会計基準)。
連結仕訳
次の通り。
| 取引 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 取引高の相殺消去 | 売上高など | ××× | 売上原価など | ××× |
仕訳例
- 連結会社間取引において発生した取引高:売上高100 売上原価100
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 100 | 売上原価 | 100 |