PDCA財務会計
更新日:2024年10月31日
公開日:2012年4月3日
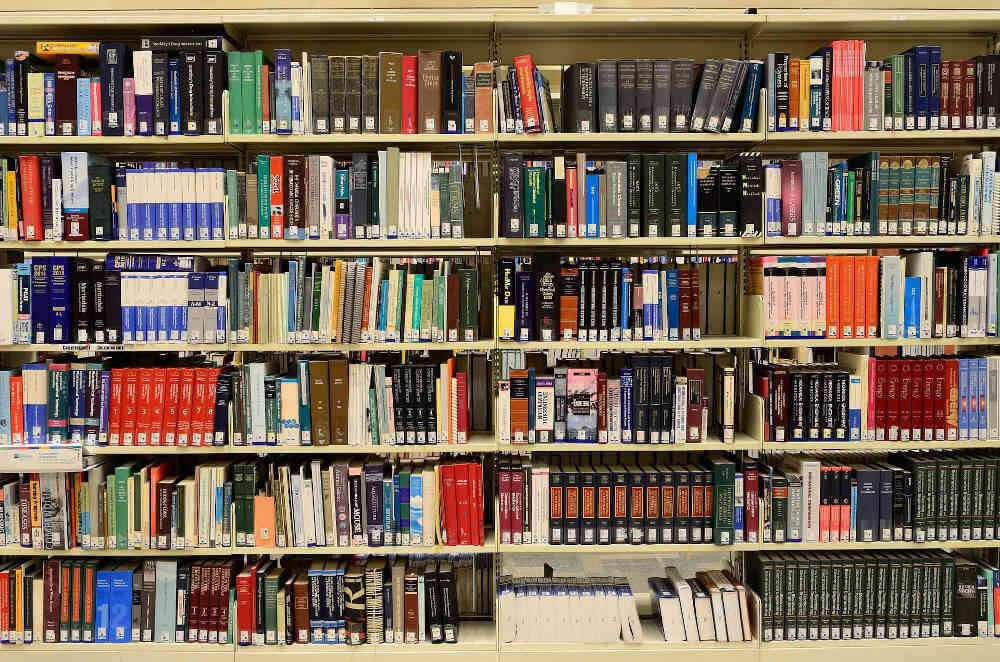
「PDCA会計」の財務会計カテゴリです。
「PDCA財務会計」では、「上場企業」を対象とした決算書(金融商品取引法に基づく会計、会社法に基づく会計)を中心に説明しますが、現状の制度会計ではなく、理論や考え方を解説している部分もあります。
当サイトについては、「PDCA会計(運営情報)」で詳しく説明しています。
決算書が役立つ時とは
皆さんは次のような場面に遭遇したことはありませんか?
決算書の知識が役立つ場面
- ・取引先から会社の売上や利益等、業績を聞かれた。
- ・銀行等、金融機関から決算書の提出とその内容説明を求められた。
- ・自社の経営がどうなっているのか知りたい。
- ・経営者から部門の予算提出を求められた。
- ・新聞やニュースで、ある会社の年度決算について報道されていた。
- ・ある会社の株式に興味があるが、購入していいのかどうか分からない。
このような場面では、決算書を読めれば困ることはありません。
会社は1社1社、ビジネスとして様々な活動をしています。そしてその活動の1つ1つが、会計(正確には簿記)という道具を用いて数字として記録されることになります。
従って会計が分かれば、その会社がどのような活動をしたのかが1件1件の取引毎に分かるのです。
さらにこれらの会計記録を年毎や月毎等、ある期間中の活動を集計したものを「決算書」といいます。
決算書を読むと、その期間中に会社がどのような活動を行ってきたのかを大局的に読み取ることができます。
以上から決算書は会社の活動を知る上で非常に役に立つものです。
会計の勉強方法
最初に会計を学ぶことで得られるメリットを知りましょう。モチベーションを上げたり保つのに役立つので、学習効果も上がりますし、長続きします。
会計学の用語は最初はとっつきにくく難しいと感じます。当サイトのように厳密な定義ではなく、分かりやすい言葉で解説した書籍やサイトで学習するとよいでしょう。
同時に簿記の学習をおすすめします。上述の通り、「ミクロ=簿記」「マクロ=会計」という関係にあります。簿記を学ぶと取引1件1件を把握できるので、会計と合わせると会社の取引毎や会社全体だけでなく、その中間である事業別、部署別、取引先別といった様々な切り口で会計データを分析できるようになります。
記事一覧
※簿記に関する記事は「PDCA簿記」に掲載。
- ・会計・簿記の勉強方法を分かりやすく解説
- ・会計とは|最も基本となる用語を分かりやすく解説(入門)
- ・トライアングル体制とは|日本の会計制度を解説(入門)
- ・資本取引・損益取引区分の原則
- ・認識・測定とは|登場場面別の使い方を分かりやすく解説
- ・現金主義とは|ポテチで具体的にわかりやすく解説(入門)
- ・発生主義とは|バレンタインチョコの具体例でわかりやすく解説
- ・実現主義(販売基準)とは|他基準との違いをわかりやすく解説
- ・収支額基準とは|会計用語を分かりやすく解説(入門)
- ・費用収益対応の原則とは|図を使って具体例でわかりやすく解説
- ・取得原価主義(原価基準)とは|会計用語をわかりやすく解説
- ・費用配分の原則とは|基本用語をわかりやすく解説(入門)
- ・出荷基準とは|会計基準上の取り扱いや開示事例も含めて解説
- ・納品基準・引渡基準・着荷基準とは|違いや実務上の留意点を解説
- ・検収基準とは|会計用語を具体的にわかりやすく解説(入門)
- ・貸借対照表の見方を初心者へ簡単に解説 | 関連記事も紹介
- ・貸借対照表等式・資本等式とは|用語解説(入門)
- ・正常営業循環基準・一年基準とは|会計用語の解説(入門)
- ・棚卸資産とは|貸借対照表や流動資産、勘定科目(仕掛品)の解説
- ・未収入金と経過勘定
- ・固定資産の区分
- ・固定資産を資産計上する理由について分かりやすく解説(入門)
- ・固定資産と時価主義
- ・資産計上と評価の考え方をまとめて解説(入門)
- ・貸倒引当金とは|貸借対照表の資産である理由や要件、計上ルールを解説
- ・負債の区分 支払手形と買掛金、短期借入金
- ・未払金と経過勘定
- ・未払法人税等と預り金
- ・リース債務と退職給付引当金
- ・純資産とは(出資や株主、株式について)
- ・資本金と資本準備金とは|制度の目的、メリット、減少(欠損填補)手続
- ・貸借対照表の分析
- ・損益計算書の見方についてわかりやすく解説(入門)
- ・財産法・損益法とは|違いと計算式を分かりやすく解説(入門)
- ・売上総利益と粗利率・原価率
- ・販売費及び一般管理費とは|内訳と参考情報、勘定科目別ポイント
- ・営業利益・営業利益率
- ・営業外収益・費用、経常利益とは|勘定科目などわかりやすく解説
- ・特別損益と当期純利益その他
- ・財務指標
- ・B/SとP/Lの財務分析
- ・真実性の原則とは|実務家フリーランス会計士が解説
- ・正規の簿記の原則とは|誘導法や会計帳簿の要件を解説(考察あり)
- ・資本取引・損益取引区分の原則とは|会計基準の逐条解説
- ・明瞭性の原則とは|企業会計が要求する開示情報を具体的に解説
- ・継続性の原則とは|現行の会計基準に沿って分かりやすく解説
- ・改正電子帳簿保存法の会計・内部統制上の運用ポイントを解説(考察あり)
- ・集団ストーカー・ガスライティングの体験談|内部統制視点からの対策を考える
- ・会計公準とは|企業実体・継続企業・貨幣的測定
- ・会計主体論とは|資本主・代理人・企業主体理論
- ・会計方針とは|注記・変更・遡及適用の取り扱いを解説
- ・表示方法の変更と遡及適用|会計基準上のポイントを解説
- ・会計上の見積りの変更と注記事項を解説
- ・過去の誤謬の注記と取扱いを解説
- ・後発事象とは(修正と開示の違い)|会計監査用語も解説
- ・偶発事象とは|引当金・注記など会計基準・処理のポイントを解説
- ・追加情報とは|具体例と注記事項など会計基準を解説
- ・継続企業の前提とは|GC注記・用語など会計基準を解説
- ・貨幣性資産・費用性資産とは|会計用語の解説
- ・クリーン・サープラス関係とは|定義・意義や成立の可否を解説
- ・資産説・資本控除説とは|自己株式の論点(会計学 上級)
- ・割賦基準(回収基準・回収期限到来基準)と廃止の理由を解説
- ・仕切精算書到達日基準は廃止なのか?|根拠を示して解説
- ・時間基準とは|収益認識会計基準上の取り扱いを解説
- ・ストックオプションとは|会計基準のポイント(用語、理論など)
- ・親会社説と経済的単一体説とは|違いと現行連結会計基準上の取扱い
- ・持株基準・支配力基準・影響力基準(連結)とは|用語解説
- ・連結・持分法の範囲の決定方法|会計基準上のポイントを解説
- ・緊密な者・同意している者とは(連結の範囲)|用語解説
- ・全面時価評価法と部分時価評価法とは|違いと現行の会計基準
- ・取得関連費用とは|概要と会計処理を解説
- ・連結貸借対照表の作成基準|概要、表示方法、科目を解説
- ・連結損益計算書の作成基準|概要、表示方法、科目を解説
- ・連結キャッシュフロー計算書の作成基準|概要、表示方法、科目を解説
- ・原則法と簡便法とは|連結キャッシュフロー計算書の用語を解説
- ・直接法と間接法のひな形|営業活動によるキャッシュフローの表示
- ・連結株主資本等変動計算書とは|概要、目的や表示区分・方法を解説
- ・連結包括利益計算書とは|概要、経緯や表示区分・方法を解説
- ・組替調整額とは|連結包括利益計算書の用語を解説
- ・連結附属明細表(金商法)とは|様式(ひな形)と概要を解説
- ・活発な市場・主要な市場・最も有利な市場とは|会計用語の解説
- ・ローン・パーティシペーションとは|会計処理・表示・注記方法
- ・回収サービス業務はなぜ資産計上するのか?|仕訳を具体的に解説
- ・ヘッジ会計とは|用語と概要の解説(上級)
- ・事前テスト(ヘッジ会計)|リスク管理方針の記載例(上級)
- ・ヘッジ会計の有効性の判定方法(事後テスト)を解説(上級)
- ・取替法・取替資産とは|仕訳や開示事例含め具体的に解説
- ・廃棄法(除外法)とは|会計用語の解説(上級者対象)
- ・減損|資産のグルーピングとは(具体例の解説 上級)
- ・減損の兆候とは|会計用語の詳細を解説(上級)
- ・減損損失の認識とは|判定方法と将来CFの算定方法(固定資産)
- ・減損損失の測定とは|会計基準・適用指針を解説(上級)
- ・将来キャッシュフローの見積方法|固定資産の減損会計(上級)
- ・主要な資産とは|決め方や変更の可否を解説(減損会計 上級)
- ・使用価値(減損会計)の計算方法を会計基準に基づき解説(上級)
- ・減損会計の割引率とは|計算方法などをわかりやすく解説(上級)
- ・正味売却価額(正味実現可能価額)・再調達原価とは
- ・資産負債法と繰延法とは|違いと会計基準の取り扱い
- ・一時差異とは|概要や会計処理などを解説
- ・移転された/投資したとみなされる額とは|会計用語の解説
- ・トレーディング目的で保有する棚卸資産とは|会計処理を解説
- ・暗号資産|期末評価と表示・注記(実務対応報告第38号の解説)
- ・組織デザインの見直し方-内部統制概念の活用例




日本の会計基準として古くから存在し現在も実務においてお世話になる会計基準。「真実性の原則」「実現主義」「取得原価主義」など、会計学を学ぶならば欠かせません。試験勉強でも各会計基準を学ぶ前の「土台」としての役割を担う論点のため、専門スクールのテキストでも最初に解説されています。